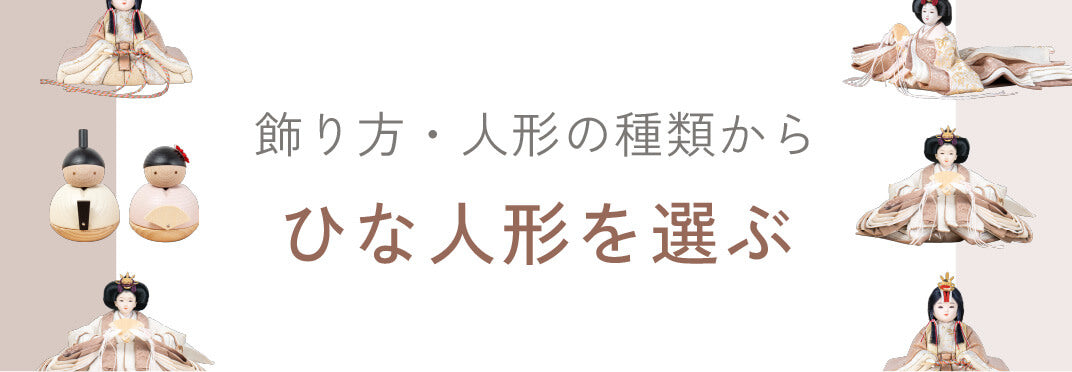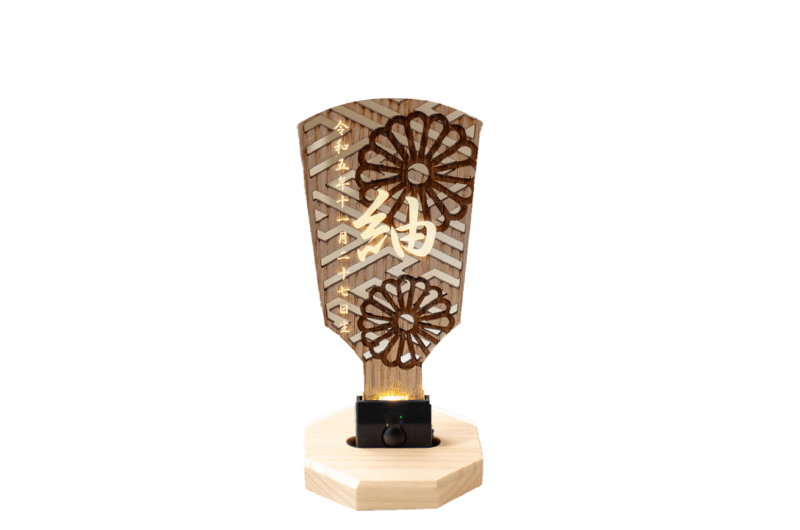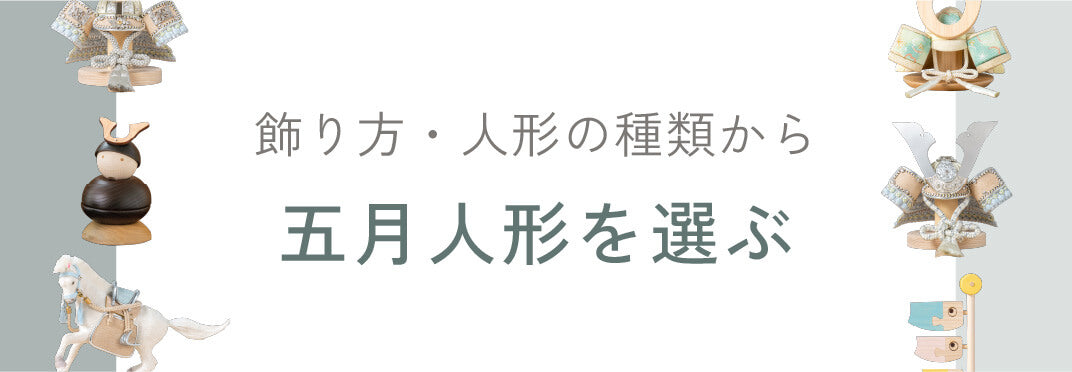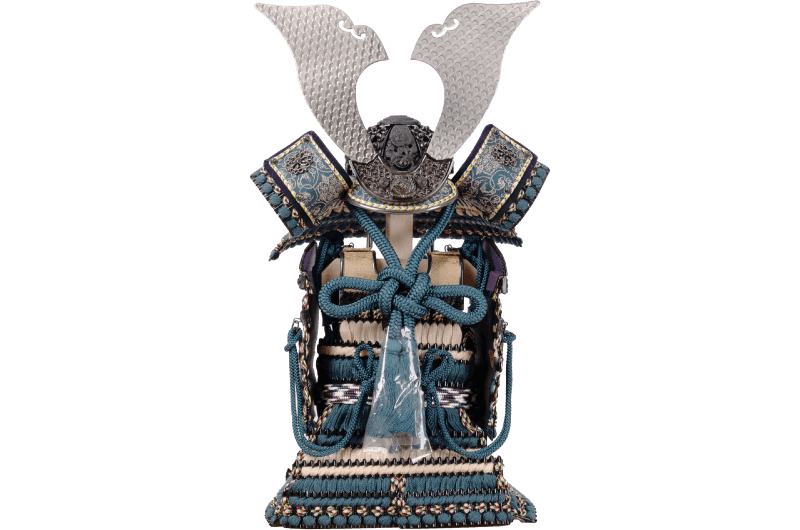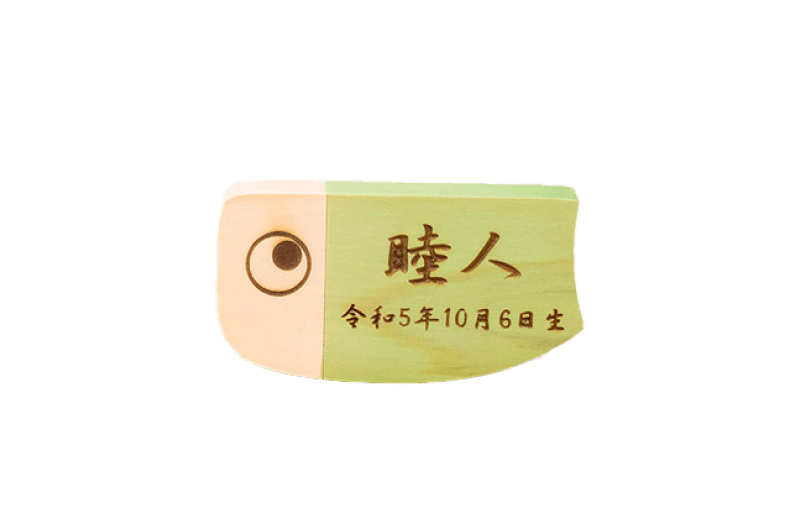女の子のお祝いひな祭り、女の子にとっては特別な日!
ひな祭りっていつからはじまったのでしょう?
ひな祭りについて詳しく知ると楽しみ方も変わってくるかもしれません。
いつからはじまったの?

ひな祭りの歴史は古く、その起源は平安時代中期(約1000年前)にまでさかのぼります。
中国から伝わった「五節句」という行事のひとつ「上巳」。季節の節目を意味する「節」のころは、昔から邪気が入りやすいとされていました。
五節句のひとつ上巳には、中国では川で身を清める習慣がありましたが、日本では紙などで作った人形で自分の体を撫でて穢れを移し川に流すことで邪気祓いをする行事として広がっていきました。
人形を流して邪気をはらうこの風習が、現在でも残るひな祭りの行事「流し雛(ながしびな)」のルーツと言われています。
ちなみに「五節句」とは?
- 1月7日の「人日(七草がゆ)」
- 3月3日の「上巳(桃の節句)」
- 5月5日の「端午(菖蒲の節句)」
- 7月7日の「七夕(星祭)」
- 9月9日の「重陽(菊の節句)」
どうやって広まったの?

その頃、上流の少女たちの間では“ひいな遊び”というものが行われていました。ひいなとはお人形のことです。
紙などで作った人形と、御殿や、身の回りの道具をまねた玩具で遊ぶもので、いまの“ままごと遊び”と言えます。
紫式部の『源氏物語』や、清少納言の『枕草子』にも登場することで有名です。
長い月日の間に、こうした行事と遊びが重なり合って、一般にも広まっていきました。
今のひな祭りに定着したのはいつ?
江戸時代中期にはひな祭りが3月3日に定められ、女の子の誕生を祝い、健やかな成長としあわせを願うための行事として定着し、今の形式に至りました。
ひな祭りが定着した江戸時代頃から、ひな人形もより豪華になっていきました。
時代と共に変化してきたのですね♪
次回はひな祭りには欠かせない食事やお供えについて触れたいと思います!